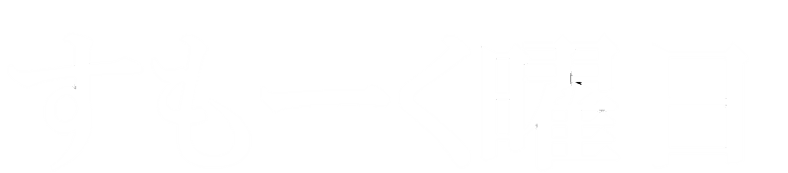初回の投稿では燻製器本体を紹介しましたので、今回から具体的な食材や料理をブログで発信していきたいと思います!
いろいろ迷いましたが、最初の食材は味つけ玉子の燻製、いわゆる「くんたま」にしました。
チーズと並び燻製会の二大巨頭と言っても過言でない一品でベタすぎかなとも思ったのですが、完成形があまりに好き過ぎるので味つけ玉子の燻製を選びました。
以下、完成までの工程です。
ゆで卵をつくる
「たまご」の漢字は「卵」と「玉子」どっち?
冒頭から横道に逸れましたが、「たまご」がつくワードは「生”たまご”」「出汁巻き”たまご”」「ゆで”たまご”」「錦糸”たまご”」「味つけ”たまご”」・・・と数えきれないほどありますが、それぞれに「卵」の字か「玉子」の二文字かで変換を迷うなぁと思いました。
なんとなくのイメージとして「玉子」は「だし巻き玉子」のように料理になったときに使い、「卵」は生の状態を指すのような認識でしたので、ネットで確認してみました。結果、それぞれ諸説あるようですが、下にまとめた二つの見解が多く見られました。
見解①(この見解が多数ネットで見られました)
【卵】生物的な意味を持ち、ふ化を前提としたもの。鳥類だけでなく魚や虫の生き物すべての「タマゴ」を指す。
【玉子】料理されることを前提とされ、鳥類に限定されたものを指す。
見解②(わたしの元々のイメージと同じ)
【卵】生(なま)のもの
【玉子】調理されたもの
・・・ということは題名の「味つけ”たまご”」で言えば、見解①にも②にも当てはまる「味つけ玉子」が正解で良いのか??と納得しかけました。
だが待てよ。「味つけ玉子」とかの表記もよく見るよな、ふ化は前提となってないし、火はもろに通っているし、どちらの見解からも外れるぞ??
「もうよくわからん!!お手上げだT_T!!」
そう思いながら、最後のあがきでネットを見ていたところ、すべてを解決する新たな見解に出会うことができました。
「基本的な意味合いはあるが、そこに明確な基準はない。」
・・・
始めからのこの文章を読んどけば良かった(^^;
ただこのオールオーケーのワイルドカード的使用が認めれるという見解を見て肩の力が抜けたせいか、これまであげた一般的な見解と若干違う別の見解が頭に浮かびました。、
見解③
【卵】黄身が崩れていない状態を保っている場合
※味つけをしてない場合に限る
例:「ゆで卵」「生卵」「卵かけご飯」
【玉子】上記以外の場合
例:「玉子焼き」「出汁巻き玉子」「味つけ玉子」
いかがでしょうか?
いずれの単語も「卵」⇔「玉子」をそれぞれ入れ換えても、違和感はないことはないですが、例に挙げたほうがどちらというとしっくりくる気がしませんか?(←カンペキ自分目線(^^;))
ということで、永遠に終わらない議論になりそうなので、「たまご」の漢字変換時はもう迷わず、自分の好きなニュアンスで変換しますw!!
殻をむくときにキレイにむけないことがある
丹精込めて卵を茹でて引き上げたにもかかわらず、むいた殻に白身がくっつきボロボロになるのはテンションが下がることは言うまでもありません。
そのため、これをやっておけば(ほぼ)失敗せず殻をむける方法を紹介します。
茹でる前に卵に穴をあける

100均一で売っているコレを使います。なければ画鋲などの針で代用可能です。
中央部分に針が付いていて卵のおしり(先が尖ってないほう)をグッと押し付けると小さな穴が開きます。それにより卵の殻と白身に隙間ができて殻がむきやすくなるそうです。
茹で終わったら、すぐに冷やす
水でジャーっと冷やすところまでは、ほとんどの方がやるのかと思いますが、そこに氷を入れて卵をさらにキンキンに冷やすとさらに温度差が広がり、穴あけによってできた殻と白身の隙間が広がり高確率でキレイな殻むきができるかと思います。
卵の味つけ
めんつゆオンリーで味つけをされる方もいるかもしれませんが、わたしは味が濃くなり過ぎる気がするのと1種類だけでなく、いろいろ入れた方が美味しくなる気がする人間なので、麦茶で少し”かさ増し”してみりんと醤油、香りづけでローリエ(香草)を入れます。

水気を切って燻製スタート
水気があるまま燻製すると煙と水が反応して苦みや酸味が強くなってしまうので、キッチンペーパーでしっかり水気を切って燻製します。

燻製は家の中でやるべき?外でやるべき?
卵だけだとスペースが余ってしまったので明太子もついでに便乗燻製させます。
写真ではわかないですが、基本燻製するときはわたしは家の外の軒先でやります。
家の中でも燻製はできますが、わたしはどちらもやった結果、現在は外でしかしなくなりました。
もちろん中、外で正解はなく、持ち家、マンションなど家の構造、家族の理解など総合的に鑑みての判断が必要になるかと思いますので、これから燻製を始める方の少しでも参考になればとそれぞれのメリット、デメリットをあげさせてもらいます。
【家の中で燻製】
・メリット
①ご近所トラブルは無縁
「煙が洗濯物につくからやんめんかー!!」のような心配がないです。
②外の天候に左右されず燻製ができる
外だと強風レベルじゃなくても、日常的に吹く風でも火がザッザーッと音を立て消えそうになる、または実際に消えてしまうこともザラにあります。
そのため、ある程度風がある日に外で燻製をしたいときは風よけを設置するなど工夫が必要になります。家のなかであれば天候は一切気にせず燻製できます。
③用意と片付けが外でやるときと比べてラク
外でやる場合、家の中から食材や燻製器を運び、終わったらうちの中に戻す手間がありますが、家の中でやればその手間は発生しない。
・デメリット
①換気扇MAXでも家の中が煙臭くなる。
これひとつにして、最大のデメリットかと思います。
【家の外で燻製】
家の中でやる場合のメリット・デメリットが逆転する
うちは娘が臭いと泣いて嫌がるしw、自分も燻製は好きですが、家の中が煙臭くなるのはちょっとイヤだったので、泣く泣くとまではいきませんが外でやることにしました。
食材の種類に合わせて燻製器から取り出す
完全に好みの世界ですが、わたしは卵はしっかり色づかせたいので15分ほど燻製させます。それに対して明太子は同じ時間、燻製するとカピカピになってしまうので10分ほど燻製したら、明太子のみ先に引き上げます。
ちなみに妻は明太子はカピカピが好きです。今回は自分が食べる用なので、ほどよく薫りが付く程度で良しとしました。焼きタラコと生タラコ、どっちが好みかとほぼ一致すると思います。(たぶんですけど)
10分経過↓

引き続き卵の燻製待ちしていたら、思わぬ珍客、トカゲさんが現れました!!
トカゲさんと燻製器のツーショットを撮らせてもらいました(^_-)-☆

※心臓なのか動脈なのかわかりませんが、持っていた手に「ドクドクッ」という強く速い鼓動が手に伝わり、それの鼓動に耐え切れなかったため、草むらまで連れていき、そこでトカゲさんとグッバイしました・・・人間の身勝手な行動に巻き込んでしまったトカゲさん、ごめんなさい<m(__)m>!!
でも外で燻製をやらなければ、こういった出会いも生まれることはなかったので、準備や天候等いろいろ面倒はありますが、外の燻製も悪くないなと思いました。(トカゲさんからするといい迷惑かもしれませんが(^^;))
完成!このカンペキなフォルムがやっぱり大好き💗

もはや味か好きというより、このツヤを見るために燻製たまごをつくっていると言い換えてもいいかもしれませんw
そしてツヤもさることながら、網目の跡も市販品には見ることができず、「自家製燻製をやってるなー(^^♪」を感じさせてくれます。
以上、初めて燻製をする過程を写真の添付とともに公開させていただきました!!
今後もぜひお目通しをいただければ幸いです!!